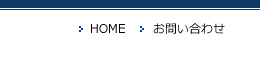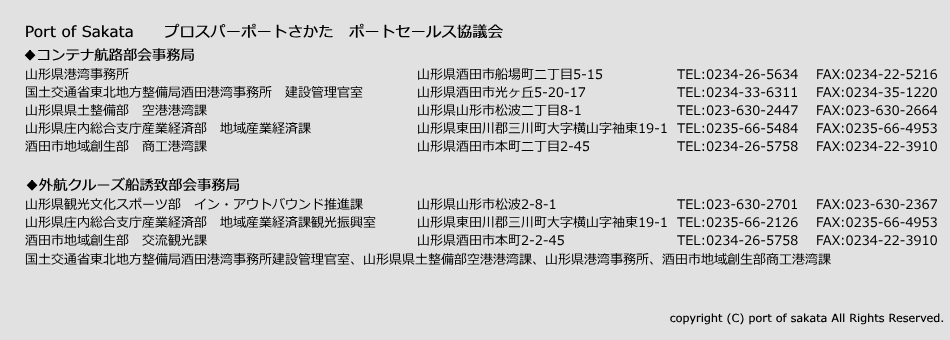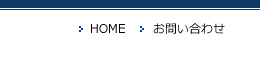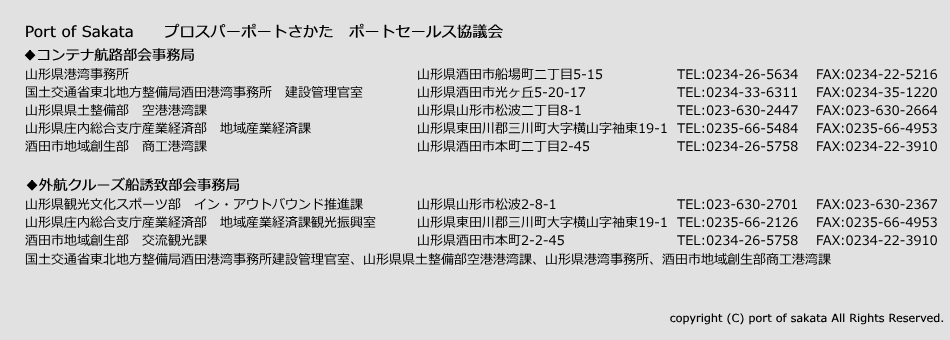|

 酒田港は最上川の河口に発達した港で、古くから日本海沿岸や内陸河川交通の要衝として多くの豪商が軒を並べ、中でも南部藩の定宿として日本海貿易に活躍した二木家、西鶴の「日本永代蔵」に北国一の米の買い入れ問屋と記述された鐙屋、日本一の地主として知られた本間家等は酒田港の象徴として全国にその名を知られている。寛文12年(1672)河村瑞賢による西廻り航路の開拓で酒田港は一層繁盛し、江戸中期には97軒を数える廻船問屋があり、嘉永・安政の頃は酒田港全盛の時代であった。 酒田港は最上川の河口に発達した港で、古くから日本海沿岸や内陸河川交通の要衝として多くの豪商が軒を並べ、中でも南部藩の定宿として日本海貿易に活躍した二木家、西鶴の「日本永代蔵」に北国一の米の買い入れ問屋と記述された鐙屋、日本一の地主として知られた本間家等は酒田港の象徴として全国にその名を知られている。寛文12年(1672)河村瑞賢による西廻り航路の開拓で酒田港は一層繁盛し、江戸中期には97軒を数える廻船問屋があり、嘉永・安政の頃は酒田港全盛の時代であった。
しかし、河口港として発達した酒田港は最上川下流部における乱流が甚だしく、また大洪水による流出土砂のため、港口の水深維持が困難であった。明治には帆船から汽船時代に変わり、船舶が大型化するにつれて港の利用度は低下し衰微をまぬがれなかった。明治17年政府は最上川航路の改良を目的とした治水工事を起こし、河口港としての悪条件を克服してきた。近代設備の整った酒田港は大型外国船の入港が目立ち昭和45年には北港地区の建設に着手、昭和59年6月には50,000D/W級第一船の入港、平成4年には中国黒龍江省との新航路「東方水上シルクロード」の開設、また、平成7年には韓国・釜山港との定期コンテナ航路が開設され、平成12年7月からはガントリークレーンやコンテナフレートステーション(CFS)上屋を備えた国際ターミナルが供用を開始するなど環日本海時代に向けた設備の充実を図った。
近年は、平成15年4月に国土交通省の「総合静脈物流拠点港(リサイクルポート)」に指定され、北港地区を中心にリサイクル関連企業の稼働が進み、リサイクル貨物の取扱量も順調に伸びている。平成17年7月には国土交通省が創設した「みなとオアシス」制度に本港地区が登録され「みなとオアシス酒田」として賑わいのあるまちづくりの一翼を担うと共に、平成18年7月に酒田港港湾計画を改定し、平成22年8月には国の「重点港湾」、平成23年11月に「リサイクル貨物機能に係る日本海側拠点港」、平成29年に「ポート・オブ・ザ・イヤー2016」にそれぞれ選定された。
酒田港周辺では風力発電や太陽光発電、バイオマス発電施設の建設・稼働も続いており、再生可能エネルギーの集積が続いている。また、港湾機能についても国際コンテナターミナルの岸壁延伸など、貨物量の増大に対応した整備が進められており、今後の更なる発展が期待されている。 |

酒田港は東経139°49’08”、北緯38°55’52”、最上川の河口に位置し、鳥海山、出羽三山に囲まれ、庄内平野の要衝にある。庄内平野は耕地整然たる水田で庄内米100万石を産する。出羽丘陵を出た最上川は、平野の中央を西北に流れ日本海にそそぎ、平野の西にある砂丘地帯は延長約35km、幅員1.5km〜3.0km、我国三大砂丘の一つとされており、果樹園や蔬菜畑として利用されている。
|
大きな地図で見る |

| 本港の波浪は季節風によるものが多く、その進行方向は大体海岸に直角方向であり、等深線は、海岸線にほぼ平行に走っている。最大波高は10.65mで西から西北西の方向である。もっとも多く見られる波は、波高0〜2.0m、波長70〜80m、周期4〜6秒である。 |

| 本港の底質は砂質であり、内港は細粗中砂に幾分シルトを含み、外港の内、最上川河口は粗中砂、港口と北海岸は細砂質が多い。 |

| 日本海沿岸は一般に秋から冬にかけて、低気圧が中国大陸または黄海方面に発生して日本海を縦走するため、海上はシベリア方面からの季節風が吹き、庄内地方の気象もそのため風が強く、酒田の強風日数は年間50日、内7割までは11月〜3月の間に多く吹く。 |

| 本港は潮差極めて少なく、日潮差30cm未満に過ぎないため、潮の満干に因る潮流への影響は微弱なものと思われる。潮流は海岸沿いに南から北に向かい0.15m/sec内外であるため、船舶の航行に支障を来すことはない。 |

| 当海域の漂砂の移動方向は、風況や波浪に支配されながらも南下する方向を示し、海岸は全体として汀線変化が小さいといえる。しかし、最上川左岸側は、河川からの供給土砂の影響も受けているためか全体的に堆積の傾向にある。 |

| 朔望平均満潮面+54cm、平均潮位+34cm、朔望平均干潮面+9cm、東京湾中等潮位0cm |

| 日和山三角点(東経139°49’49”、北緯38°55’11”)から323度1,600mの点を中心とする半径3,450mを有する円内の海面、並びに最上川河口(南防波堤基点)から上流約2,600mの地点まで、導流堤に沿い幅120mの最上川河川水面及び新井田川新内橋下流の河川水面。 |

| 北緯38°57’04”、東経139°47’15”の地点を中心として500mの半径を有する円内の海面。 |
|
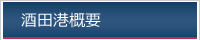
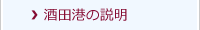
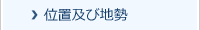






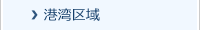




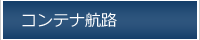

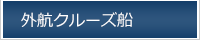
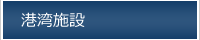
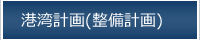
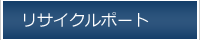

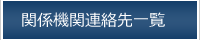

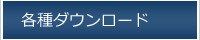
 |
|